「満洲国」からの引き揚げ 満洲生まれのつぶやき(14)
木村 敏之(宇治久世)
国府軍の支配下
撫順病院のK院長から伝染病院を国府軍の陸軍病院とするので、日本人看護婦を大量に出すようにいわれてきた。条件もよく、前回には一足違いで就職できなかったので直ぐにもち帰り皆と相談することとした。看護婦達は躍り上がって喜んだというが、何しろ一躍高給取りになれるのだから。しかし、一抹の不安が残り、よく考えるように申し伝えておいたところ、翌日「よく相談したところ、国府軍の病院には勤めないことになった」と言う。
そろって帰国したいという意思が勝ったのであろう。それでも一部の看護婦は応募したようだ。5月になり、ぼちぼち内地送還が始まるらしいとのことで皆、勇気づけられ、待っていればそのうちに順番が回ってくると喜んでいた。まさしく果報は寝て待てのことわざのように、6月になると奉天辺りから引き揚げが開始され、まず特に職のない難民から先に移動するとのことであった。避難と生活困窮者(まさしく私たち一家も立派な難民)であるわれわれは、N院長がその難民グループの救護班として残留徴用を免れたこともあり撫順病院のK院長には大変感謝されていたことが推測される。人の運命はまったく一瞬先を計り知れないものであると述懐されているのが大変印象的である。
話は少し転じて待ちに待った帰国を前にして、満洲の良いところの風景描写をしたいのだが、筆者は当時5歳頃にてはっきりとした記憶もなく、ここは「文芸春秋vol.61」の9月号に特集―1983年「されど、我が満洲」には筆者の父が応募したハロンアルシャンの写真も出ている―に頼り、詳しくは小生と同じコースを引揚移動された方が吉林近郊の描写をされているのでそれに譲りたい。
冬の満洲は外が防寒衣類の必要なマイナス20度以下でも社宅の中は暖かく、水汲み用のソリで2階の窓から外へ滑り降りた記憶があるぐらいで、男の子の憶えていることはそれくらいのことであろう。
特集には、当時筆者より1〜2歳年上の女性の方(仮にN・Hさん)が同じ道をたどられて、北国の春について記述されている。なかなかの名文で(無断で失礼ながら)そのまま引用させていただく。「北国の春は遅い。しかし一度にやってくる。丈高い楡の新芽の浅緑、夢のように飛んでくる柳じょう。新緑に混じる梨の花の白。杏の花の淡紅。真紅の野バラ。薄紫のライラックと低く頭を下げ可憐な白い鈴をぶら下げた鈴蘭。しかし一番忘れがたいのは芍薬である。濃い紅の芽は鮮やかに花のごとく、白ボタンに似た気品高い真っ白な花はもひとつ地味で清楚である」。筆者には当時の記憶にこのような情景は全くない。この方も、終戦後1年をかけて内地送還の目処がつき親子7人が無事に内地に着いたことをその同じ文の中に書き寄せておられるので紹介させていただいた。これを読んだ筆者も生れ故郷の情景に明るさとロマンが加わった気がするのである。

二階まで積もった雪。社宅からソリで滑り降りるの図(著者描く)
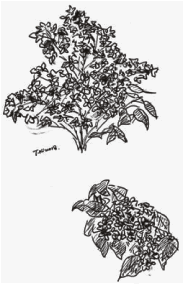
街角に見られるライラックの花(著者描く)
【京都保険医新聞第2657号_2008年9月22日_6面】









